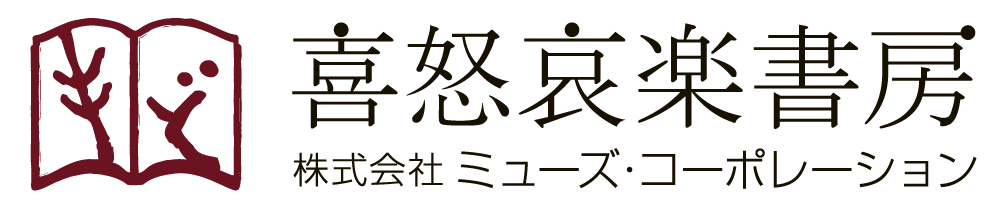4月26-27日、新潟県長岡市の野積で一泊吟行会がありました。
これは、長岡市で月1回催されている「信天翁俳句会」(4月28日の句会より第一長岡句会と改称)のメンバーお薦めの宿に、指導にあたる「銀化」主宰 中原道夫氏に泊まっていただきたい、それであれば一泊吟行をしよう! ということから実現の運びに。
そこは「お宿 まつや」という、江戸時代からの歴史を持つ茅葺屋根の古民家。

2日とも暑すぎず寒すぎず、海も山も光り輝くまさに吟行日和。
三々五々集まった参加者は荷物を置くや、その後マイカーに分乗して照明寺へ。

ここは、真言宗智山派の名刹で良寛は境内にある密蔵院に3度(45、70、72歳)仮住まいしたと言われています。

住職からお寺の説明を受け、黄色・黄緑・緑色系の花を咲かせる御衣黄桜を見るために、一同狭い高所へ。

良寛が仮住まいした密蔵院に行くと、なんと…。

ちょうどその時、守宮(やもり)が。

守宮は夏の季語、そして漢字では「家守」とも。
家に住むと家を守り、災いを避けてくれるという言い伝えに由来してのこと。
うーん、句材になりそう。
その後は、航海の安全を祈願して奉納した船絵馬のある白山媛神社や、弁慶の手堀り井戸、オルゴール塔等を見ながら、案内図にあるロマンス街道の話題に。
「どこがロマンス街道? 」「えっ、この道がそうなんだ」「ロマンス詐欺だな」などと軽口をたたきながら、いざお宿に戻り句会へと。
まずは中原道夫氏より解説。

吟行の勘どころ
たくさん見ても今回は4句しか出せないということもあって、もうこれで作ろうと来る途中や事前に孕んでいく場合も多い。
意識が分散しないようにその場に行ったら見ないという人もいる。
私も来る途中でパパっと考えて、あとは本当に見たものを混ぜようと。
そういう意味では、今日は割とちゃんと見たもので作っていることに感心した。
例えば「御衣黄桜」や「船絵馬」で作った人。
「船絵馬」はわざわざ500円払って見たわけで、元をとらないともったいないと(笑)。
でもどうしても素材が偏ってしまうというか、みんなが詠っているため後塵を拝する形になるので難しい。
そうしたところは誰も見ないかもしれないが、自分しか見ないもので作るという手はあるかと思う。
吟行は、最初はそんなにうまくは句が出てこない感じがすると思うが、行く度に少しずつ腕が上がってくる。
そのうちに今日はこの椿で作ろう、石蓴で作ろうという風にだんだん臍が決まってくるので、あとは自分を信じてそこに突き進む。で4句だったら、5句、6句と多めに作って、自分の中で選句して…ここが大変なんです。
これもいけどこっちも捨てがたい、そこをどうしようと選句ができてくると、自ずと俳句を作るのも上手になる。

吟行と机上の両輪そして句会
人の句を見るということは句会に出るということ。
他人の句を見て私もここを詠いたかったのに先を越された、という悔しい思いをすることも大事。
私も最初吟行はあまり好きじゃなかった。でも、詠み込みの言葉1つをいただいてイマジネーションで作る机上俳句と吟行、要するに実際に見たものの両輪で作っていくのが上達の方法だと言われている。
それ以上に1人で机にしがみついていても、なかなか上達はしない。
句会に出て、自分以外の人がどういう句を作るか読ませていただく、その中で採るということ、先句するということがとても自分の力になるということを頭に入れた方がいい。
特に吟行に来た場合のポイントは、やはり「まつや」というお店に泊まらせていただく、そういうところが眼の付けどころだと思う。
あと良寛もたくさん出てきたが、良寛は季語じゃないので、無理やり入れるとその分だけ言葉が減る。船絵馬もそう。
これを書くなら文字数が取られるぞ、と覚悟した方がいい。

表現の幅を広げる
守宮も出ていたが、別名はヘキコともいう。漢字では「壁虎」。
「壁虎」なんて出てきてもわからないと思うが、何年も俳句をやってると守宮=壁虎とわかる。歳時記を見たら、句の脇に出ている傍題(別称)を見てください。
曼珠沙華の傍題には彼岸花、死人花など10近くある。
それらを内容に準じて使い分けるのも1つの手。
そういう風にしていけば、言葉が難なく増える。
小学生で言えば、6色のクレヨンしか持ってない感じ。
子どもの時は色を混ぜて使うなんてことも知らないから、その色を生で使う。
そのうちパステルなんかも買ってもらうと、パステルの色を合わせ、それが終わると今度は水彩絵具になる。
そうすると12色の絵具でも、いろんな色を作れるようになる。同様にいろんな言葉や季語の言い替えも知ってくると、その内容に準じてもっと表現の幅が出てくる。
春夏秋冬、同じところへ行っても現れるものが違ってくる。特に食べ物。昔は吟行で句ができないとなると旅館の朝飯で作っていた。ハンバーグじゃダメだが、日本食はシーズンの宝庫だから。あー今日はできなかったわと思っても、明日どんな朝食が出てくるかわからない。
日本の料理は季節がいっぱい詰まってるから、困った時のお膳頼み。お膳の中の何かを拾えば何句か足せる。
あとは外へ出た時の風景や花だとかを混ぜれば、吟行は怖くない。ということで、どんどん吟行好きになっていただきたいと思います。
中原氏の特選
出迎へは見越の松や夏館 すみれ子
つちふるや見えざる佐渡の横たはり わ子
「霾(つちふる)」は日本中どこにもあるが、芭蕉の「荒海や佐渡に横たふ天の川」を踏まえ、この土地に挨拶をしている。
あいにく佐渡が見えなかった、だから見えないのは当たり前じゃないかという人もいるが、そうではなくて心眼、心の目で見えない佐渡を見る。
見えるものばかりを信用せず、見えないものを詠むということも1つの方策なのではないかと思います。
中原氏普通選
眼目は葉に擬態せし桜かな 敦子
良寛のかつて草庵やもり棲む 文人
見はるかす海は茫洋春愁 智子
風薫る佐渡と弥彦の境より 亮太郎
御衣黄ゆ石仏ひとつ倒れをり わ子
このあとは、場所を変えてすぐに楽しい宴へ。
お皿には季語がたくさんあり本来であれば、学んだことを活かして句材を拾えばいいのでしょうが、ビールを前にそんなことはもう埒外に。
楽しい時間はあっという間に過ぎ、その後は囲炉裏で日本酒を。

翌朝はお宿の裏の山に行くと、あけびの蔓やわらびがそこここに。
実質14時から翌日の9時までの約19時間という短い時間でしたが、五感を刺激し続けた充実の時。
知らない人同士も俳句という共通言語ですぐに打ち解け、寝食をともにする。
吟行って俳句って、大人の遠足って楽しいなと、年甲斐もなく感じたのでした。
(木戸敦子)